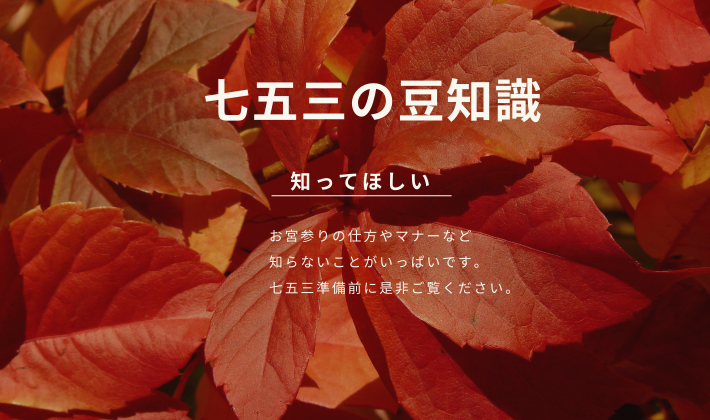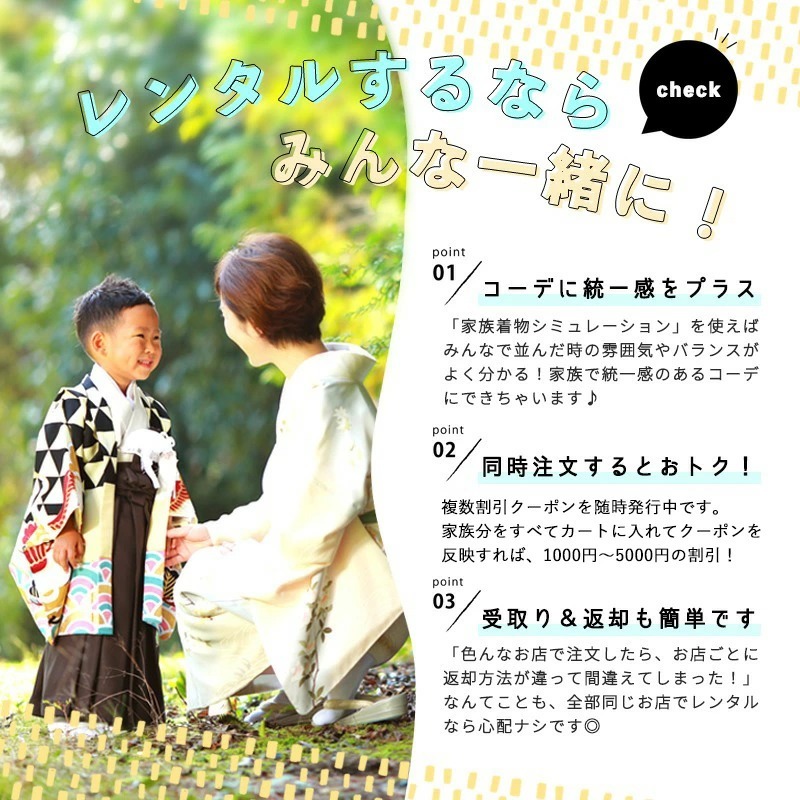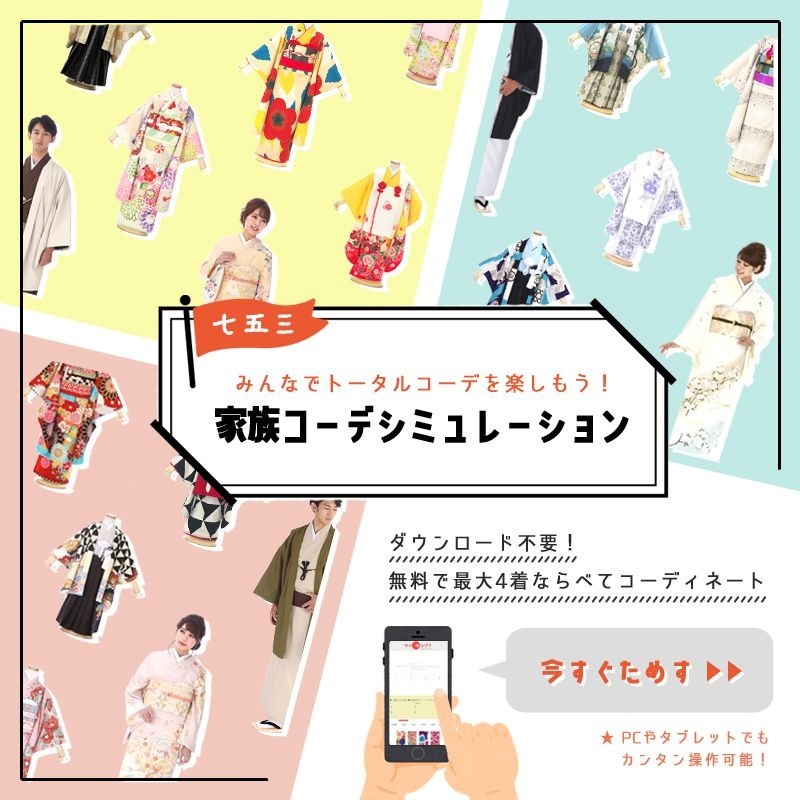秋の神社で、可愛い子供たちが着物姿でお参りする光景を目にすることがありますよね。
でも、自分が親になって子供の七五三のお参りに行こうと思った時、参拝のためにどのような準備をすればいいのか、しきたりやマナーについてよく知らなくて困ってしまうこともあるでしょう。
このページでは、七五三の神社参拝に関する基本的なマナーから興味深い豆知識まで、詳しくご紹介しています。
お参りの場所はどこにしよう? 七五三の神社選びのポイントは?
七五三のお参りプランを立てよう!
神社選びの第一歩は家族で話し合って、決めましょう。
日本には大小さまざまな神社がたくさんありますから、どこに行くか迷ってしまう人も多いかもしれません。
実は七五三には特定の神社に行かなければならないという決まりはありません。
大切なのは、家族みんなが一番いいと思う神社を選ぶことです。
一般的に神社を選ぶ理由としては、次のようなポイントが挙げられます。
- 自宅周辺の神社 身近でアクセスも便利。
- 移動や境内の利便性が高い神社 楽々と参拝できる。
- 有名な神社 名前を知っていると安心感がある。
それぞれにメリットがあります。
- 自宅周辺の神社
-
古くから、日本では地域の守り神にお参りする習慣が根付いていました。
これが氏神様と呼ばれる存在であり、七五三や結婚式、お宮参り、初詣など、人生の重要なイベントにおいても参拝が行われてきました。
現代では、氏神様への意識が薄れつつありますが、お子さんの成長に感謝の気持ちを込めて氏神様にお参りすることは、素晴らしい選択です。
特に自宅から近い神社は、お子さんにとっても負担が少なく、時間も節約できる参拝しやすい場所と言えます。 - 移動や境内の利便性が高い神社
-
移動距離が長くなく、お子さんが飽きずに楽しめる場所を選びましょう。
駅からのアクセスが良く、電車やバスを乗り継ぐ必要のない場所がおすすめです。
さらに、駐車場の数も確認しておきましょう。また、神社の境内環境も事前に調査が必要です。
ベビーカーを利用する場合には、階段しかなくエレベーターがない場所は避けるべきです。
また、広すぎて移動が大変な神社も存在します。
安心して訪れるためには、事前にホームページをチェックしたり、問い合わせをしたりしましょう。 - 有名な神社
-
七五三を特別な雰囲気で祝いたいなら、厳かな雰囲気が漂う有名な神社がおすすめです。
大きな神社では七五三専用のプランや休憩場所、食事処が用意されており、安心して参拝できます。
ただし、有名な神社は七五三の時期には多くの人で賑わいます。
混雑による疲れや予約の取りづらさなど、大きな神社ならではの注意点もありますのでご注意ください。
七五三参りの正しい方法とマナー
「いつもお参りはしているけど、正しい方法がよくわからない」という方も多いのでは?
七五三の際、家族で自信を持って参拝するために、神社参拝のポイントを5つご紹介します。

- 服装
-
神社での参拝は、神様へのご挨拶の儀式です。
特に祈祷を受ける場合は、拝殿で儀式を受けます。
そんな時、ジーンズやTシャツは失礼です。正装が基本です。
お子さんも家族も、フォーマルな服装を心掛けましょう。
お母さんは和装、お父さんはスーツが一般的ですが、ルールはありません。
特別な機会なので、「家族全員で和装を!」もいい思い出になるかもしれません。 - 神社到着から参拝までの作法
-
STEP鳥居で一礼

鳥居くぐる前に一礼しましょう。
先は神様のいる場所、心込めて挨拶の一礼です。STEP参道の端を静かに歩く広い参道、端を歩いてください。
境内も神聖、心静かにお過ごしください。 STEP手を清める
STEP手を清める境内に入ると手水舎と呼ばれる、お清めをする場所があります。
ここでは柄杓で手と口をすすぎ、穢れを落とします。
お清めの仕方も作法がありますので、覚えておきましょう。
手水舎(てみずや)の作法は神社によって微妙に異なる場合もありますので、参拝する神社のルールに従うようにしてください。
また、お子さんの手口を洗う際には、着物を濡らさないように気をつけましょう!


- 柄杓を右手に持ちます。左手で柄杓の先端を支えるようにします。
- 柄杓を垂直に立て、水を取ります。水は一度で十分です。
- 右手で水を受け、左手に移します。左手で口をすすぎ、口を閉じて水を吐き出します。
- 残った水を右手に戻し、右手で口をすすぎます。
- 最後に右手で柄杓の先端を洗い、柄杓を元の位置に戻します。
- 手を軽く振って水を切り、最後に一礼して手水舎を離れましょう。
STEP二礼二拍手一礼


参道を進んで、本殿の前に着いたら、神前でお参りです。
基本の作法は「二礼二拍手一礼」。- まず一礼して、お賽銭を入れます。
- 次に二礼二拍手をして、名前と願い事を伝えます。
- 最後に一礼で終わりです。
深い2度のお辞儀(二礼)は、神様への敬意と感謝を表しています。
二拍手は、鈴を鳴らすのと同じ意味と考えられており、拍手の音で邪気を払うとされています。
拍手を 打つ意味には、神様に自分の訪問を知らせる意味があるとの説もあります。
この「二礼二拍手一礼」の順序で参拝を行うことで、神様への敬意と感謝の気持ちを示し、心身を整えるとされています。STEP祈祷を受ける参拝するだけでなく、七五三のご祈祷を受けるのも大事な行事のひとつ。
心の中に感謝と祈りを込めて、神様へのお願いを述べる時間です。
神職が祝詞(のりと)を読み上げ、お子さんの成長と未来への祝福を祈ります。
拝殿へ上がる際にはコートを脱ぎ、場合によっては靴も脱ぐことがあります。
快適に移動できる服装を心掛けましょう。
参拝だけでなく、祈祷を受ける場合には、初穂料(はつほりょう)が必要になります。
初穂料は、祈祷のお礼として神様に納める奉納金です。
お金を直接手渡しするのではなく、「御初穂料」または「初穂料」と書かれた熨斗袋に入れるようにしましょう。
初穂料の相場は神社によって異なりますが、一般的には5,000円から10,000円が一般的とされています。
金額に迷う場合は神社に問い合わせてみて、「相場はどのくらいですか?」と尋ねることもできます。
金額に悩むことは普通のことで、恥ずかしいことではありませんのでご安心ください。 - 七五三当日の一般的なスケジュールは?祝いの日を完璧に楽しむ方法
-
七五三の1日の流れは様々ですが、一般的なスケジュールを紹介します。
家庭や状況によって異なるので、柔軟に調整しましょう。無理せずに余裕を持って、お子さんも楽しめるスケジュールを作りましょう!
朝、衣装を着付けます。
美容院での着付けは事前に予約し、家族全員の準備をスムーズに済ませましょう。
お子さんのぐずりや移動の心配がある場合は、お母さんが着付けやセットをする選択肢もあります。
先ほどの「神社到着から参拝までの作法」で紹介したように、神社でのマナーを守りながら参拝しましょう。
神社参拝時にはマナーを守って参拝しましょう。
七五三シーズンは参拝者が多く混み合いますので、神社までのアクセスや、車で行く場合には駐車場の有無なども事前に確認しておくと安心です。
七五三シーズンは混雑するのでアクセスや駐車場の確認が安心です。
家族が揃い、主役のお子さんも可愛く着飾っている参拝の日!!
特別な参拝の日に写真館で撮影する家族も増えています。
大きな神社では七五三プランに写真撮影も含まれることもあります。
予約は早めに確認して写真館を予約しましょう。
参拝と撮影を当日にするのは大変な場合、別日に前撮りをすることもあります。
移動距離などを考慮して無理のないプランを立てましょう。
メインの行事が順調に進んで一安心です。
家族が集まる特別な日には、午前中に行事を終えて家族揃ってお昼の食事会が多いです。
子供連れでも利用しやすいレストランやホテルを予約しておくと、行事の疲れやお腹すいてもスムーズに食事会へ移動できます。
七五三のお祝いメニューがあるお店もありますので、事前にリサーチしておくと良いです。
衣装を汚さないように注意しましょう。
お子さんにとっても慣れない衣装での食事は大変です。
レンタル衣装の場合、両親も汚さないかとヒヤヒヤするので、食事前に着替えることをお勧めします。
まとめ
神社巡りからマナー、1日の流れまでご紹介してきましたが、七五三のイメージは湧きましたか?
当日は家族で相談しながら場所とスケジュールを決め、スムーズな参拝を心掛けましょう。
お子さんもご家族も思い出に残る素敵な1日になるよう、事前の準備をお忘れなく!

七五三の着物 NEW TREND
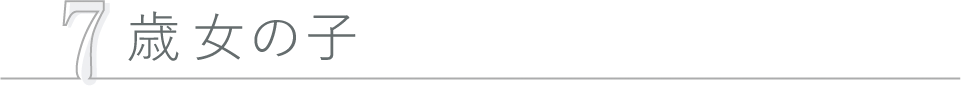
対応身長110cm-125cm
明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊
昔から晴れ着と言えば正絹



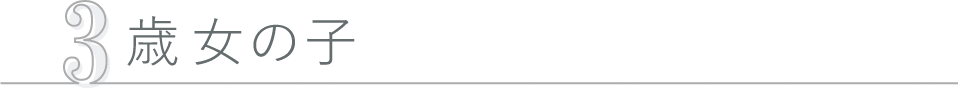
対応身長85cm-100cm
明るく鮮やかな色合いやポップでかわいいデザインが豊富な高級化繊
昔から晴れ着と言えば正絹



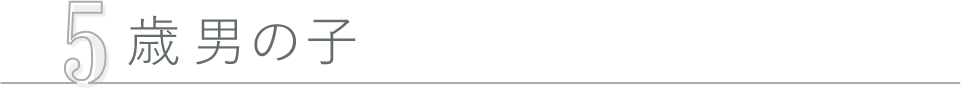
対応身長103cm-118cm
■袴タイプ
■和洋2WAYタイプ
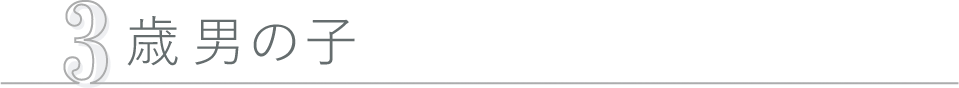
対応身長85cm-98cm
■袴タイプ
■被布タイプ
■和洋2WAYタイプ